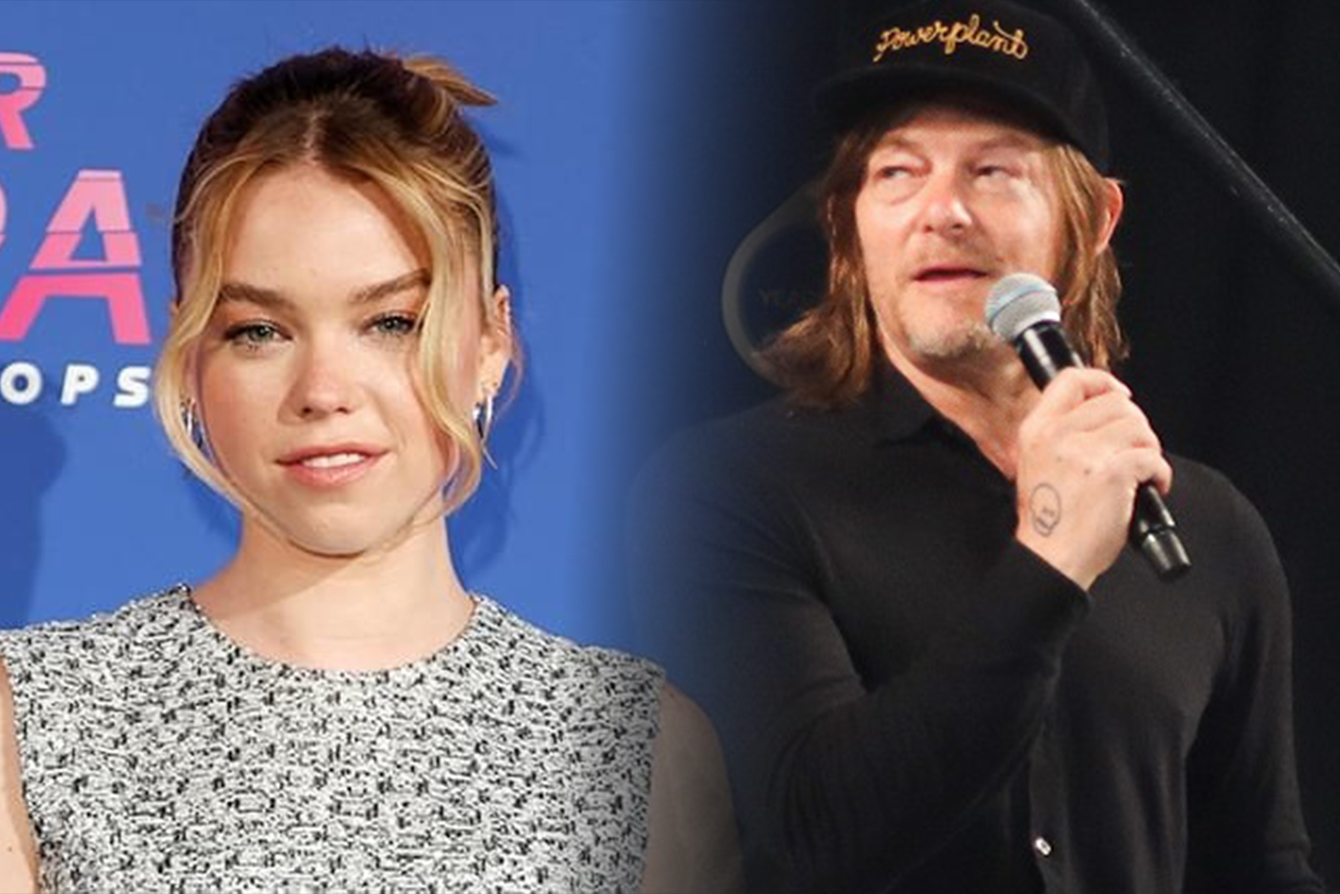本サイトのコンテンツには、広告リンクが含まれています。
※この記事には映画『8番出口』のネタバレが含まれています。ご注意ください。
流行りに流行りまくったゲーム『8番出口』。
もはやゲーム実況者の登竜門的な作品にもなっているが、そんな『8番出口』が二宮和也主演でまさかの実写映画化。
基本的にはこれといったストーリーがないのも魅力でもあるのだが、そんな『8番出口』をどのように映画化したのか気になったので鑑賞してきたので、感じたことを正直に書き残しておこうと思う。
先に行っておくと、筆者はゲームは未プレイ(実況は見たことがある)、予告編もまともに見ないままで映画館に足を運んでいる。
結果、この『8番出口』という映画は、ループの恐ろしさを楽しむのと同時に、不快なポイントもある、絶妙なバランスの映画だった。
映画『8番出口』異変一覧
先述の通り本作はゲーム『8番出口』を原作としている。
そのため映画の中でもゲームと同じ異変が出てくる一方で、オリジナルの異変も描かれている。
ここでは後述の内容をより理解しやすくするために、映画で描かれた異変を一覧で紹介していく。
・蛍光灯の並びが乱れている。
・上部からヘドロのようなものが垂れてくる(一部映画オリジナル)。
・コインロッカーから赤ん坊の泣き声が聞こえる(映画オリジナル)。
・ポスターの目が動いている。
・おじさんが笑顔で追いかけてくる。
・主人公の元カノから電話があり、何故か8番出口の通路から電話をしている(映画オリジナル)。
・黄色い蛍光灯になっている(映画オリジナル)。
・清掃員詰所のドアノブが真ん中にある。
・女子高生が話しかけてくる(映画オリジナル)。
・偽物の外に繋がる階段が現れる。
・上部看板の「8」の文字が逆になっている。
・少年の母親が現れる(映画オリジナル)。
・右の壁の扉の一つが開いている。
・停電が起き、排気口から大量のネズミのモンスターが現れる(一部映画オリジナル)。
・濁流が襲ってくる(一部映画オリジナル)。
ゲームに出てくる「ポスターが徐々に大きくなる」や「監視カメラ」「タイルマン」などは映画では登場していない。
ゲームと同じ異変が出ればファンサービス的には楽しいが、映画オリジナルもあったほうが謎解き要素もあるので、このバランス感覚が重要だったとも思える。一方で映画オリジナルの異変が親切にもわかりやすかったので、結果的に映画の8番出口自体そこまでの謎解き要素は無い。
ストーリーが無い『8番出口』に入れたストーリーとは
個人的に『8番出口』の実写と言えば、YouTuberのすしらーめんりくの動画なのだが、それは置いておこう。
ゲーム版『8番出口』には基本的にストーリーはない。
しかし映画ではそうはいかない。
本作には主に三人の登場人物が存在する。
一人目が主人公である二宮和也さん演じる「迷う男」。二人目は”おじさん”の愛称でも有名な河内大和さん演じる「歩く男」、そして最後は浅沼成さん演じる謎の子どもであり、劇中では二人の男と行動を共にする「少年」だ。全員具体的な名前は明かされていない。
この三名に加えて8番出口に迷い込んでいないが、迷う男の元カノである小松菜奈さん「ある女」も登場する。
歩く男については後述するとして、迷う男にはある程度バックグラウンドが用意されている。
劇中では派遣社員として職場に向かう途中に8番出口に迷い込んでしまっている。駅から出る途中で別れた彼女から電話が来て、自分の子どもを妊娠したことも告げられている。
子どもに関して明確な答えを出せぬままに8番出口に入ってしまった迷う男は、その名の通り人生に迷いに迷いまくっているという設定となっている。日雇いのような派遣の仕事と、どっちつかずな元カノとの会話などを含めて、常に優柔不断で流されてきた人生であることがうかがえる。
年齢設定は不明だがおそらくそこまで若くもないだろう(二宮和也さんは執筆時点で42歳)。
そんな人生の迷子になっている男が8番出口に迷い込んでしまうのが本作の物語の軸となっており、謎の子どもとの出会いや、はからずも自分の人生を振り返る異変を通して、人間的に成長(したのかはわからない)するまでが描かれている。
『8番出口』キャラ設定の掘り下げは最小限
『8番出口』はおそらく若い層もターゲットにした映画であることは想像に固くない。主にゲーム実況者によって広まった作品であるため、YouTubeなどにネイティブな世代も観客である。
そのために飽きられないためなのか、冗長なストーリーや、登場人物の過去を掘り下げるような演出は極力排除されている。
それでも回想シーンのようなものが無いわけではない。
厳密には回想ではないのだが、迷う男が見る、子どもと妻となった元カノとの未来(と思しき)のシーンや、結果的には異変のひとつではあったが、突然かかってきた元カノとの電話での会話シーンなど、このあたりは迷う男のキャラクターを掘り下げる演出になっている。
雰囲気で今までの人生で流されるままに生きていたことがわかるような構成は、二宮さんの演技力も相まってわかりやすかった。正直二宮さんの演技力頼りなところもあるが、そこはさすがとして言いようがないだろう。
NPCだったおじさんを掘り下げたのは面白い
本作にはこれ以外にも歩く男と少年が登場する。
特に歩く男はゲームにも登場する、ただひたすら8番出口に繋がる通路を歩いている男であり、ゲームで言うところのNPCだ。そのビジュアルの再現度の高さも本作のPRポイントになっていた。
実はこの歩く男も8番出口に迷い込んでしまった人間であったことが明らかになる。
異変を探しながら脱出を試み、その中で謎の少年と出会うのだが、焦るあまりか異変を見逃し、少年の気づきすら無視するほどだった。
歩く男の8番出口の場合は、すれ違うNPCは女子高生(花瀬琴音)に変更されている。この女子高生が話しかけてきて、徐々におかしくなるのはホラー映画でよく見るシーンで、言ってしまうとベタな演出だったので、あまり驚きは無い。怖かったけど
そして最後はゲーム版にも登場する外につながると思しき階段に騙され、少年の制止を振り切って階段を登っていってしまい、そのままゲームオーバーとなる。
あからさまに異変であることはわかるのだが、もはや歩く男の精神状態は限界に達していたと推察できる。
8番出口で脱出に失敗した人間は、NPCとして永遠に歩き続けることになることが示唆され、おそらく女子高生も以前は人間であったことが考えられる。ガラケーのようなものを持っていたり、少し前の女子高生の流行りの服装をしていることからも、数年以上前に巻き込まれた可能性がある。
正直おじさんの正体に新解釈を導入することは、賛否両論はあると思う。8番出口という怪異の恐ろしさとその被害者の末路を描けるのは面白いが、やはりおじさんは正体不明の不気味な存在のままであってほしいとも思う。
おじさんのかつての人間としての姿が描かれたことで、少なからず感情移入ができてしまうため、彼への不気味さが少々薄れてしまう。
結論は受け取る観客次第ではあるが、映画によって8番出口の恐ろしさと世界観の幅を広げることはできたと受け取ることもできるだろう。
『8番出口』絶妙に苛つく登場人物
見出しにもある通り、これまで登場してきた三人の登場人物は絶妙に苛つくシーンが多い。
迷う男の喘息設定はどこへ
迷う男は異変には気づくほうではあるが、途中で元カノからの電話を装った(と思われる)異変にまんまとハマり、0番に戻ってしまう。
次に現れた黄色い色味になった通路の異変で、ついに発狂してしまい、嘔吐をした後に背負っていたカバンを投げ捨て、中身を放り投げて地面にしばらく寝そべるシーンがある。
気持ちはわからなくないが、彼には「喘息持ち」の設定がある。
いつ脱出できるかわからない状況でカバンの中をぶちまけ、さらにはそのまま放置して進むというのは明らかにおかしすぎる。
映画冒頭では数回喘息の発作が起きた後に持ち歩き用の吸引機で発作を抑えるシーンがあるのだが、カバンをぶちまけた後は都合を合わせたように喘息の描写は出てこない。
ぶっちゃけると筆者自身も喘息持ちであり、実生活ではもしもの備えで吸引機は常備している。
わざわざ喘息持ちの設定を追加したのだから、後に発作が悪化してしまい命の危機に…みたいな展開を予想していたのだが、そんなこともなく、まるでそんな設定は最初から無かったように映画は終わっている。
これ、本当に必要だったの?
正直一番腑に落ちなかった部分である。
歩く男、もうすこし落ち着け
歩く男については脱出を急ぐあまりに異変を見逃し、さらに少年の気づきもスルーしてしまうというのは先述した通りだが、脱出に失敗した人間を描きたいのならば、ゲーム版でもあるようなもっとわかりにくい仕掛けを入れることで、脱出の難しさを描くべきだったように感じる。
明らかに罠であることがわかる(しかも出口の数字の順番としてもおかしい)外に繋がるような階段に簡単に引っかかるのはあまりに強引だ。何としてもすぐに脱出しなければならない事情があるならばまだわかるが、そのような掘り下げはそこまでされていない。そのために正直彼の行動にはイラつきを感じてしまった。
それこそ歩く男に喘息設定を追加し、いまにも命の危険が迫っているときに階段が現れれば、それにすがってしまう気持ちも理解することができただろう。
もうすこしうまいやり方があったのではないかと思う分、歩く男については非常にもったいないキャラクターだと感じた。
少年、喋れたんかい
そしてこの記事ではようやく触れるが、謎の少年も行動が少々不可解だ。
歩く男と行動しているときは異変には気づきながらも、一切口を開いて喋ろうとしない。歩く男が話しかけても口を開かない。
「これは映画などでありがちな失語症的なものか?」と思ったが、次に迷う男と行動してからはあっさりと喋る。
おいク*ガキ、なんで最初から話さないんだよ?
何らかのショックで話せなくなったのかと言われると、そうでもなさそうだ。
彼は母親に心配してもらいたくてあえて迷子になったと語っており、偶然にも8番出口に迷い込んでしまったのだ。これだけで話せなくなったかと言われるとなんとも腑に落ちない。
100歩譲って突発的な失語症になっていたとして、喋れるようになったきっかけは何だったのだろうか。
本作の異変には各登場人物のトラウマや過去を抉るような演出がある。少年は母親の幻想を見るといった異変だった。
母を見るやいないや大声で名前を呼び、駆け寄ろうとするところを迷う男に止められている。これが言葉を取り戻したきっかけだったのだろうか?
鑑賞後に考えてみたが、結局結論は出なかった。
三人ともがなんとももどかしい苛つきを感じてしまうキャラクターとなっており、せっかくの設定もうまく活かしきれいない、またはあまりにご都合主義過ぎて、非常に残念に感じたポイントだった。
ほんと、君たち何だったんだよ
『8番出口』あの「少年」は何者だったのか
これまで触れてきた謎の少年は、劇中では主人公の迷う男の子どもであることが示唆されている。
本作の中心の時間軸ではまだ迷う男の子どもは誕生していないが、8番出口という怪異においては時間軸がひとつという常識は通じないのだろう。
数年後の未来の世界で8番出口に迷い込んだ少年が、父であると思しき迷う男と出会った…と思えば話は簡単である。
しかしどうにも矛盾があるのも確かだ。
まず挙げられるのは少年は父親に会ったことがないということだ。
このことから迷う男は8番出口からの脱出に失敗し、そのまま息絶えた(NPCとなった)結末が示唆されていたが、実際はそうではない。
詳細は後述だが、迷う男が8番出口から脱出したのならば、少年が父親に会ったことがないというのは矛盾が生じる。
もちろん実は脱出できていない、または脱出したが踏ん切りがつかずに元カノのもとには向かわなかったということもあり得るだろう。いずれにしてもこの映画では明確な答えは示されていないため、結論を出すことはできない。
次に思いつくのは異変のひとつとして現れた少年の母だ。
この母は迷う男の元カノの姿そのままである。そのため少年が「ママ!」と叫んだ姿を見ると迷う男は戸惑いのリアクションをしている。なぜなら彼にとってまだ彼女は母ではないからだ。
しかし先述のように時間軸がねじれているのならば、こういったこともありえなくはない。
一方でそうなると父親に会ったことがないという少年の発言の矛盾にたどり着き、先述の通り堂々巡りの8番出口状態だ。
そして最後に異変として襲ってきた大量の濁流(というより明らかに津波として描いている)に迷う男と少年が巻き込まれるシーンだ。
ここで溺れてしまった迷う男はあるイメージを見ることになる。それが海岸で遊ぶ少年の姿を見守る自分と元カノの姿だ。どうやら少年は自分のことを父親であると認識しているようで、父である迷う男に海で拾った貝殻をプレゼントしている。
これは8番出口の中でお守りとして少年が男に渡していた貝殻と同じ形状をしている。
このシーンは迷う男の未来、少年にとっては過去を示しているようなシーン(父親に会ったこと無いと言っているが)となっているが、おそらくこれは男の想像によるものだろう。
現に迷う男はその直後に意識を取り戻し、溺れる少年を水面まで上げて看板の上に乗せて救出している。おそらく少年を自分の未来の子どもに無意識になぞったことで、そういった少年を助ける行動に繋がったのだろうと考えることができる。
そのためこのシーンにおいては、迷う男と少年が親子であることを示すものとは言い難い。
それでは結局二人は他人同士だったのか?それとも親子なのだろうか?
その答えはわからない。これは何度考えても答えにたどり着かないようにしている、制作者側が観客に仕掛けた8番出口だったのだ。
考察好きを煽ることで、映画の宣伝にも繋がる効果があるため、こういった演出も映画の流行りの一種と言えるだろう。
『8番出口』不快な音楽演出
本作は音楽も印象的に使用されている。
まず印象的なのはフランスの作曲家であるモーリス・ラヴェルが1928年に作曲したバレエ曲の『ボレロ』だ。
終始同じ2種類のリズムが続くのが特徴で、この”繰り返す”部分が8番出口のループと結びつけていると思われる。
一度聞けば耳に残る曲としても有名で、日本の映画やアニメなどでも多用されている。個人的には『デジモンアドベンチャー』と映画『交渉人 真下正義』が記憶に残っている。
『8番出口』においては冒頭と最後に使用され、迷う男がイヤホンで聞いている音楽として流れている。最初と最後に持ってくることは、おそらくこの作品のループ性を表していると思われる。後述するが、それを思わせるような演出も最後に存在する。
この『ボレロ』についてはは全然良い。個人的にも好きな曲なので、むしろもっとやれと推進していきたい。
しかしそれ以外の音、特に下に挙げる2つはかなり不快な部類だった。
一つは赤ん坊の泣き声。
これは本作においても不穏な予感や、異変としても使用されている。
映画冒頭での電車内で突然泣き出してしまい、車内に重苦しい空気が流れるシーン。次は異変の一つで映画オリジナルのコインロッカー内から聞こえる赤ん坊の泣き声。これはかなり不気味である。
最後は突然の停電の中で排気口から現れたネズミのモンスターたち。このネズミには人間の耳や鼻、そして口がついており、その口からは赤ん坊の泣き声が発せられるというものだ。
あからさまにホラーの演出のために使用されていることはよく分かる。
元々ホラー映画ではよく赤ん坊の泣き声は使用されることも多く、人間の本能として赤ん坊の泣き声は不快に感じるようにできているのだ。そのため手っ取り早く不快感を与えたいなら、この声を使用すれば良いのだ。
そんな安直な理由ではないと思うが、本作においては不快演出のひとつとして機能している。
ちなみに先述の人間の部位がついたマウスの一部は実在する。
バカンティマウス、通称”耳ネズミ”と呼ばれており、ネズミの背中に人間の耳のようなものを移植した実験が行われている。また2016年にはiPS細胞の実験で作られた耳軟骨をネズミの背中で培養するといった実験も行われた(グロ画像の一種でもあるため、検索は要注意)。
ここまでは音楽や効果音の使用については許容範囲。物語上の意味もあるため、そこまで問題視はしていない。
しかし最後の金切り音の演出は論外だ。
これは8番出口で角を曲がり、おなじみの風景が現れるたびに流れる。不穏な演出を強調するために使用しているようで、ホラー映画などではあるあるな音だ。
しかしその頻度があまりに多い。
角を曲がり、「さぁ、異変を見つけるぞ!」と観客が心のなかで思うときにこの金切り音だ。言葉を選ばずに言うと、馬鹿の一つ覚えのように使用しまくっている。
これがあまりに不快だ。怖いとかではなく、シンプルに作品の演出として不快なのだ。
赤ん坊の鳴き声は許せるが、この音についてはセンスが無いとした言いようがない。もっとやりようがあっただろうに、なぜこのような演出になったのか疑問だ。ちなみに予告編でもこの音は使用されている。
使い所をしっかりと見極めれば気にするほどのものではないが、一度気づいてしまうとより不快さが増していく。この音が聞きたくないがために、映画を再度鑑賞することを躊躇うほどだ。
ホラーとして怖がらせながらも、耳に優しい音を使ってもらえるとありがたいところだ。
まとめ『8番出口』結局脱出できたのか
そしてやはり気になるのは、主人公は8番出口を脱出することができたのかという点だろう。
結論から言うと、「わからない」。
ゲームのルール上、すべての異変を見つけ出して無事に8番出口までたどり着き、脱出ルートである階段を下ると、普通に人々が歩く地下鉄の駅にたどり着くのだ。
映画冒頭ではその駅から派遣先の職場に向かう予定だったが、迷う男は改札の中に入り、彼女に電話をし、おそらく病院に向かうために電車に乗る。
しかしその電車内では映画冒頭であった突然泣き出してしまう赤ん坊と、困惑する母親、そしてそれを理不尽に怒鳴りつけるサラリーマンという全く同じ状況が繰り返されている。
冒頭では母である女性を助けることなく、そのまま音楽を聞き続けていた迷う男だが、最後はその仲裁に入ろうとして動き出すシーンで映画は終わっている。
実際に仲裁に入って女性を助けたのかは描かれていない。そのため動き出そうとしたが、結果的には思いとどまってしまった可能性も考えられる。
ただ8番出口をきっかけに迷う男は迷いを捨てて、自分の意思で人生を歩もうとしているといったことが示されているようにも思えるシーンでもあるだろう。
しかしこの映画はループホラーの「8番出口」だ。もしこの一連の流れすら異変だったらどうだろうか?
そうなれば知らぬうちにまたループの罠にハマり、8番出口から脱出できなかったということになる。これは当該のシーンで再び『ボレロ』を聞いている演出からもそれを想起させることもできる。(ちなみにゲーム版の出口は地上に向かう階段だったが、映画版では地下に向かう階段になっているのも気になるところ)
また未来の子どもであると思われる少年が「父親に会ったことない」という言葉にも繋げやすい。
結果的に迷う男が脱出したかどうかは明確にはされていない。これはこの映画を見た観客が答えを出す余白として残されているのだ。
ちなみに少年についても脱出できたかどうかは明確にはされていない。
個人的には脱出できたと思いたいが、8番出口の理不尽さとこれまでの異変の人の心の無さを考えれば、脱出失敗の方が全然あり得る。
この映画では巻き込まれた登場人物たちが明確に脱出できたかどうかはこの映画には盛り込まれていないし、さらには8番出口という怪異が何だったのかといった正体も明かされていない。
8番出口の正体は明かさないほうが良いと思うが、映画の結末としてこれは脱出成功だったのか、それとも失敗だったのか、『8番出口』という映画は観客に起きた異変だったのかもしれない。
映画『8番出口』は2025年8月29日より劇場公開中だ。
※この記事には映画『8番出口』のネタバレが含まれています。ご注意ください。
流行りに流行りまくったゲーム『8番出口』。
もはやゲーム実況者の登竜門的な作品にもなっているが、そんな『8番出口』が二宮和也主演でまさかの実写映画化。
基本的にはこれといったストーリーがないのも魅力でもあるのだが、そんな『8番出口』をどのように映画化したのか気になったので鑑賞してきたので、感じたことを正直に書き残しておこうと思う。
先に行っておくと、筆者はゲームは未プレイ(実況は見たことがある)、予告編もまともに見ないままで映画館に足を運んでいる。
結果、この『8番出口』という映画は、ループループループループループループループループループループループループループループ。

映画情報サイト「Ginema-nuts(ギネマナッツ)」の編集部です。
【広告】
【広告】